
DX Office
営業におけるDXとは?成功のためのポイントや実際の事例を解説します!
新型コロナウィルスの影響により、これまで緩やかだったIT化の波が一気に押し寄せてきた昨今。
とりわけ、今まで「対面方式」が当たり前だった「営業」での影響は大きく、ウィズコロナ・アフターコロナでも企業が生き残っていくためには、営業部門でのDX導入が必要不可欠です。
では、どのようにすれば、営業におけるDXを実現させることができるのでしょうか。
今回の記事では営業におけるDXについて、成功させるためのポイントや導入の具体例について解説します。
目次
1.営業におけるDXとは何か?

DXの定義
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、もともとスウェーデンのウメオ大学の
教授であるエリック・ストルターマン氏が2004年に提唱した概念です。
教授はDXについて「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」と定義しました。
これを受けて、経済産業省は国内の産業におけるDXを、以下のように定義しています。
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」。
(参考:経済産業省「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX 推進ガイドライン)」
つまり、DXとは、企業戦略の中にデータとデジタル技術を組み入れて活用し、新規事業や新サービスなどを展開するための手段と言えます。
また、同じく経済産業省から「2025年の崖」について問題提起したDXレポートが出されています。
これによると、約8割の国内企業では、事業部門ごとに構築された既存システムが複雑化・ブラックボックス化した「レガシーシステム」を抱えています。
レガシーシステムは属人的な保守・運用で継承が難しく、IT人材やコストを浪費することから、経営戦略上の足枷や高コストの原因となり、DX実現の妨げになっています。
DX化が実現できずにデータを活用することができなれば、市場の変化に対応できなくなりデジタル競争に敗れてしまいます。
さらに、システムの維持管理費の高額化や保守運用人材の不足から、システムトラブルやデータ滅失などのリスクが高まります。
その結果、2025年以降、最大12兆円の経済損失が毎年発生する可能性があるのが、2025年の崖のシナリオです。
2025年の崖を回避するためには、複雑化・ブラックボックス化したレガシーシステムを2025年までに刷新し、新たなデジタル技術の活用によるDX化を実行する必要があると政府は主張しています。
(参考:DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~(サマリー))
営業におけるDX
それでは、営業部門におけるDXとは何でしょうか。
営業部門では、単なる業務の効率化といったことは目的ではありません。営業部門におけるDX導入の最大の目的は「売り上げの増加」にあります。
この目的を達成する手段として、顧客の購買行動を分析して、それにマッチするように自社の営業プロセスを再構築します。
そして、デジタルツールを活用することにより、顧客ごとのニーズに対応した営業アプローチを実現する必要があるのです。
2.営業におけるDXの必要性

従来は主に対面で行われていた営業活動ですが、そもそもなぜ営業部門でDXを導入する必要があるのか。その理由についてご紹介します。
生産性・効率の向上
一つ目の理由は、生産性・効率の向上です。たとえば、今までは営業活動に伴う移動時間や交通費といったコストがかかっていましたが、オンライン商談であればこれらのコストは発生しなくなります。
また、従来の営業活動では見込み顧客を見つけることが難しく、テレアポや訪問営業では多くの労力がかかる割に直接成果に繋がりにくく、却って迷惑がられることもあります。
もちろん、このようなアプローチだけでも、今までは成果を出すことが可能でした。
しかし、少子高齢化によって人口減少が続いている国内において、営業パーソンが減少していく中、従来の営業アプローチだけで対応することは困難になってきています。
とはいえ、その分営業パーソンに長時間労働を強いることは、ライフワークバランスの観点からも望ましいものではありません。
そのような企業からは、優秀な人材が離れてしまうリスクもあります。
これらのことから、従来の非効率的な営業活動を見直して、1人当たりの生産性・効率性を向上させることが必要です。
たとえば、メーカーであれば、販売した製品の利用時間や回数などのデータを集め、これらのデータから稼働状況を分析します。
そして、適切なタイミングで保守点検などのアフターサービスや他のサービスを提案することが可能です。
また、メーカー以外の業種であっても、MA(マーケティングオートメーション)を導入し、見込み顧客の情報を集積しつつ、適切なコンテンツを提供します。
ニーズが顕在化したタイミングで、対面による営業アプローチをすることで、従来よりも生産性を向上させることが可能です。
マネジメントの効率化
従来であれば、管理職は、営業担当者と顧客がどのようなやり取りをしているか把握するためには、営業の現場に同行する必要がありました。
オンライン面談を導入することで、自席にいながら面談に参加することが可能となり、もし同席ができなかったとしても、録画した会話を後から確認することができます。
また、DXによるツールを活用することで、営業案件の進捗状況などを把握することができます。これにより、社員に対する指導も効果的に行えるようになります。
属人的な体制からの脱却
営業部門が属人化しやすい要因として、顧客情報や案件に関する詳細な情報が営業担当者のところにしかなく、組織として共有されていないことが挙げられます。
このことによる弊害として、「担当者が不在のとき、他の社員で対応ができない」「個人の経験や知識によって営業スキルにバラつきがあり、成果に差が出る」「前任者から引き継ぎを行ったが、情報に漏れがあった」といったことが発生するリスクがあります。
また、良い人材を育成・獲得できたとしても、そのような人材は他社でも求めていることから、長期間雇用し続けることが困難です。
DXの導入により案件に関する顧客情報やノウハウなどのデータを集約し蓄積することで、突発的に担当者が不在になったとしても、代わりの社員で対応が可能になります。
さらに、商談の会話や対応記録をデータ化することで、顧客の動機やニーズも把握することができ、今後の受注予測が立てられるようになります。
顧客情報やノウハウといった情報を見える化することによって、属人的な体制から脱却して営業スキルの標準化に役立ちます。
加えて、顧客に関する情報を営業部門だけでなく、他部門でも共有することで自社にとって貴重な財産となり、強みとなるでしょう。
3.営業DXを成功させる4つのポイント

DXは、無計画に導入しても失敗に終わります。営業部門でのDX導入を成功するために意識する4つのポイントをご紹介します。
①DXの目的を明確化する
まずは「何のためにDXを行うのか」という目的を明確にすることが重要です。
その目的によって、導入するべきツールや手法も異なります。
「競合他社がDXを導入したから」「DXを導入するのがトレンドだから」というような表面的な動機では、結局中途半端なものにしかならず、時間とコストだけかかってしまったという事態になりかねません。
常にゴールから逆算して、DXの導入を推進するようにしましょう。
②営業プロセスを再構築する
従来の営業スタイルでは、顧客の元に何度も訪問することで成果を出すことが常識でした。しかし、このような固定概念は捨てる必要があります。
既存の営業プロセスを軸にしてDX導入を検討してしまうと、ツールの利用幅に制限が出来てしまい、本当に達成したかったことが実現できなくなる可能性があります。
導入を検討しているツールでできることと活用方法を整理した上で、再構築する営業プロセスに組み込むようにしましょう。
③営業DX推進に最適なチーム作りをする
営業のDXを推進するためには、DX導入前後にサポートする体制を整備しておく必要があります。ただし、チームの全員がDXの知識を持っている必要はありません。
一見、DX推進のメンバーはDXの知識を持っている人材だけで構成した方が効率が良いと 思うかもしれません。
しかし、営業DXを成功させるためには、現場を理解している社員の起用が重要です。
経験豊富な営業部門の社員であれば、たとえDXやITに関する知識がなかったとしても、顧客のニーズを把握しています。
また、DX推進のチームリーダーは、なるべく自社の社員から選任しましょう。もし、適切な人材がいなければ、コンサルタントなどに依頼する方法もあります。
しかし、外部に依頼する場合も、DX導入初期の一定期間に留めるなどして、コンサルタントに丸投げしないようにするべきでしょう。
④自社に合ったツールを選ぶ
経営陣や管理職、あるいはシステム部門などの意見で導入するツールが決められてしまう事例がありますが、実際にツールを使用するのは現場です。
一方的に、現場で導入するツールを決められた場合、現場が実際に求める機能と乖離してしまい、結局、有効に活用されないことが起こりえます。
DXを推進するツールを選定するときには、どのような機能が現場では必要とされているのか、ヒアリングすることが大切です。
そのうえで、全体設計をして、自社の目的と親和性の高いツールを選ぶのがポイントです。
4.営業DXの具体例

リード獲得
一つ目は、リード獲得にDXを取り入れる方法です。
急速にデジタル化が進んでいる中、リード側の消費行動は変化してきています。
何らかの商品やサービスを購入するときには、事前にインターネットで情報収集することが当たり前になってきました。
特にスマートフォンの普及によって、より一層この傾向は強まっています。
例えば、洗濯機を購入する場合、昔であれば実際の店舗に行って、スタッフの話を聞いてから購入する方法が一般的でした。
しかし、現在では、事前に企業のホームページや比較サイトなどで機能やレビューを確認した後、最後の確認のために実店舗に行き、購入するのは最安値のサイトで、といったプロセスに置き換わってきています。
こうした消費行動のポイントは、以下の3点です。
- ネットなどの非対面方式で意思決定の大半を済ませる
- 自分のタイミングで情報収集と購入を行う
- 顧客との接点がマルチチャネル化している
そして、この変化はBtoCだけではなく、BtoBでも起きています。購入の意思決定において、対面での営業活動は、もはや絶対ではありません。
そのため、かつては主流だった訪問営業やテレアポなどの方法は、時間やコストがかかる割に望むような成果を出しにくいです。
また、訪問営業やテレアポは、社員への負担が大きいという点からも望ましくはありません。
DXを導入することによって、従来の非効率的なアプローチを刷新し、効率的にリードを獲得することが可能になります。
具体的には、メールや自社のWebサイトといったデジタルチャネルを活用した手法です。
訪問営業やテレアポが1対1だったのに対して、この手法は一度に大勢の潜在顧客にアプローチをかけることができます。
顧客育成
二つ目の顧客育成とは、見込み客の購買意欲を高めて、購買する状態までアプローチする手法です。既存の顧客をリピーターにすることも意味します。
自社サイトや展示会などで獲得したリードに対して、様々な手段でアプローチすることで、自社の製品やサービスを購入したいと思うリードに育てていきます。
具体的な手法としては、主に以下の3つがあります。
- メール配信
- 自社サイト
- 電話・DM(ダイレクトメール)
一つずつ詳しくみていきましょう。
一つ目の、メール配信は手軽でコストもかからず、開封やリンクの反応も簡単に把握できます。また、セグメントによって文面や件名を簡単に変えることも可能です。
反面、その手軽さから多くの企業でも同じように営業のメールを配信していることから、自社のメールが埋もれる可能性が高い点には注意が必要です。
二つ目の自社サイトですが、これは単に会社概要や求人情報を掲載したサイトだけを指していません。
自社製品の紹介サイト、ブログ、動画などweb上にある自社のコンテンツを総称して自社サイトと表現しています。
これらのコンテンツを有効に活用することで、リードの属性や意思決定のタイミングに応じて、自社独自の情報を伝えることができます。
三つ目の電話・DMについては昔から使われている手法であり、コストや時間がかかるデメリットがあります。
しかし、商談に持ち込むためのアプローチとして電話は今でも有効であり、DMも形として残るため、メールより効果的な場合もあります。
これらの手法は、ツールを活用することで、メリットを最大限に活かし、デメリットを最小限に抑えることができます。
重要なのは、1つの手法だけを実行するのではなく、様々な手法を組み合わせてリードに対して多角的にアプローチすることなのです。
顧客分析
三つ目の顧客分析では、商談化された案件や既存顧客の分析を行います。
SFA/CRMの活用により、リードごとの購入履歴や内容を記録し、一度購入したリードにリピートを促すことにより、ロイヤルカスタマーに育てることが可能になります。
SFA(Sales Force Automation)は営業支援、CRM(Customer Relationship Management)は顧客管理を意味し、代表的なツールとしてSalesforceが挙げられます。
どちらも営業活動に関わる概念ですが、役割は異なります。
SFAは、リードに営業アプローチをかける上で、案件や商談の進捗を記録し、営業活動をサポートすることが主な役割です。
一方のCRMは、顧客のデータベースを管理・分析して、顧客と継続的な関係を作り、生涯価値を高めることが役割になります。
重要なのは、MA、SFA、CRMの導入を別々に考えないことです。MAはリードを発見して育成することはできますが、商談化された案件や既存顧客を管理することは向いていません。
MAの導入だけでは、案件の担当者が誰で、商談の進捗がどうなっているかということが把握できないため、せっかく獲得したリードに効果的な営業アプローチがかけられません。
すべてが連携することで、マーケティングと営業活動の効率が最大化できるのです。
5.企業の営業のDX事例

DXを導入したことで、既存の営業体制の抜本的な改革に成功した3つの事例を紹介します。
富士通の事例
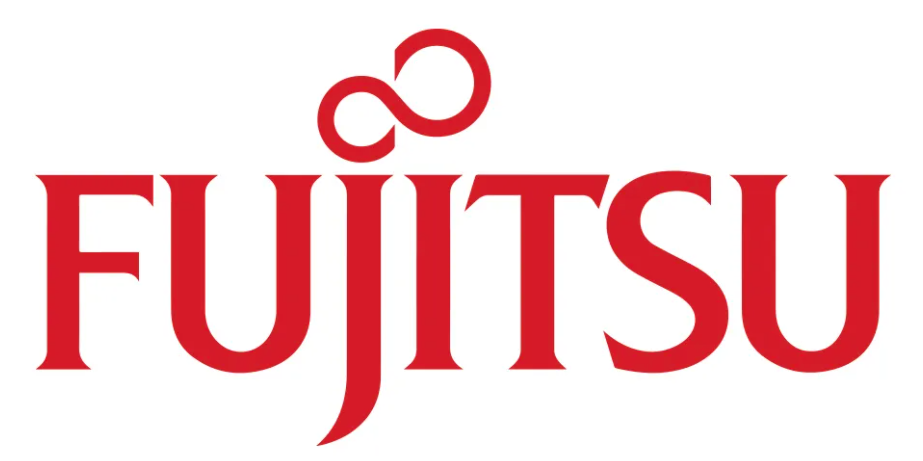
DXを担う立場である富士通は、営業職を廃止し、ビジネスプロデューサー職に改める改革を実施しました。
この改革の目的は、顧客が持っている経営課題を解決し、また顧客と共に新しい価値の想像を構想することを実現することにあります。
ビジネスプロデューサー職は単なる名称の変更ではなく、顧客を直接サポートし、価値提供をリードする役割を担っているのです。
富士通のような営業DXを成功させるためには、DX導入の目的を明確化し、他部門間で連携することが欠かせません。
大和ハウス工業の事例

大和ハウス工業では、LOC(ロック)システムと呼ばれる仲介型プラットフォームを構築することで、営業の生産性を向上させています。
LOCシステムは、不動産の有効活用を希望する土地所有者と、新規事業を展開するための拠点を求めるテナント企業のニーズを結びつける役割を担っています。
従来の営業スタイルであれば、仲介企業の営業担当者が地主を個別訪問したり、テナント企業を募集する作業を行うなど、人件費や時間のコストが問題になります。
大和ハウス工業の仕組みは、ホットリードに対するアプローチができるため、効率的に営業をかけることが可能になります。
テスラの事例

海外の事例として、テスラは、2019年に一部の店舗を閉鎖し、オンラインでの車の販売にシフトすることを発表しました。
現在では他社でも実施されている車のオンライン販売ですが、テスラはその先駆けであり、これまでの自動車業界の常識を覆す変革でした。
店舗がないことによる試乗ができないデメリットに対しては、購入後7日以内または1000マイル(約1600キロメートル)以内の走行距離であれば、全額返金するという対応をとっています。
テスラの事例はリスクも大きく、現場からの反発もありますが、成功すれば他社との差別化ができ、競争優位を実現できるでしょう。
6.自社に合ったDXを進めよう
営業部門におけるDX化の推進は、従来の営業プロセスにおける課題を発見し、生産性・効率性を向上させることに役立ちます。
また、今まで「経験」や「勘」などに頼りがちであった属人的な営業スタイルを、顧客情報のデータ化やノウハウの共有によって見える化することで、営業パーソンによるスキルの標準化、他部門間での連携や案件の進捗上の把握といったことも可能になります。
様々なメリットをもたらす営業部門のDX化ですが、成果を得るためには、DXの目的を明確にすることが大切です。
そして、DX推進チームによるバックアップのもと、既存の営業プロセスを再構築した上で、自社にあったツールを選定する必要があります。
今回ご紹介した事例以外にも、戦略的にDX化に取り組んでいる企業は多くあり、今後はデジタルツールを駆使して、社会の変化に対して柔軟に対応することがますます求められます。
株式会社CENTOでは、各種WEBサイト、アプリ、デジタル広告を通じた集客支援、WEBシステム開発事業やSalesforce領域に特化をしたリソース支援のサービスなども行っております。
DX推進をご検討の際には、ぜひお気軽に下記URLからご相談ください。


 DX Office
DX Office 



