
DX Office
【徹底解説】DX推進におすすめの資格とは!?
「うちの会社でもDXを推進しよう!」と決めたものの、調べてみたら資格がたくさんあって分からない…。そんな悩みはありませんか?
実際インターネットで調べてみると、たくさんの資格があって、どれが普段の業務にあっているのか分かりづらいですよね。闇雲に資格取得を進めるのも、時間やお金を無駄にしてしまい無駄に進めることもできません。
そんなあなたに、今回、DX推進が円滑に進む資格をご紹介します!
この記事では、おすすめの資格と、資格を生かせるおすすめの職種も併せてご紹介します!
目次
1.まずはDXを知ろう

まず、DXについて軽くおさらいをしましょう。
DXとは
DXとは、「企業がデータやデジタル技術を駆使し、お客様の要求に答えながら業務効率化をしていくこと」です。
参考までに、政府が発表しているガイドラインも見てみましょう。
「デジタルトランスフォーメーションを推進するための ガイドライン (DX 推進ガイドライン) Ver. 1.0」より
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジ タル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのも のや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。
参考:20181212004-1.pdf (meti.go.jp)
2.DXを取得する意義

それでは、企業にとってのDXの必要性とはなんでしょうか。実際に下記のようなポイントが挙げられます。
AIで生産性を高める
これまで人の手で実施していた作業を、機械の導入などによってより速く的確にできるため、時間短縮やミスの低減につながります。
コスト削減
企業にとって、昨今求められている「安く品質の高い製品」を制作するには、コスト削減は何よりの重要な目的の一つです。機械の導入などは始めはコストが高いですが、上記のように生産性を高めることができ、いずれ大きな利益になります。また、余分なコストの削減にもつながり、新たな事業を始めることもできます。
3.DXの知識を必要とする職種

では実際に、企業においてDXを必要とする職種を見てみましょう。
プロデューサー
プロデューサーは、よく耳にしたことのある職種の一つだと思います。
この職種は、「世間の流行りを把握し、それに乗って企画や製品を制作し、またその制作において必要な人材や費用を調達する人」で、いわゆる「総責任者」という立場になります。
そのため、以下のことが必要となります。
・市場を読み解く力
・集団をまとめ、その集団がより良い動きができるよう導く力
ビジネスデザイナー
ビジネスデザイナーとは、「ビジネスを始めるにおいてどのように進めていくのか計画を作成し、それを実行し上手くビジネスを進めていく職種」です。
そのため、以下のことが必要となります。
・発想力
・企画を提案する力
アーキテクト
この職種は、英語で「architect」と書き、建築家や設計者などの意味があります。
ITの世界においては、「経営的な視点において、ビジネスやITの課題を分析し、解決するための対策を立て、それを実行する人」です。
そのため、以下のことが必要となります。
・ITスキル
・問題解決能力
データサイエンティスト/AIエンジニア
この職種は「データを分析し、それに基づいて合理的・論理的に判断を行えるようサポートする人」です。
企業の今後の方針を決める場などにおいて、データに基づいて判断できるよう助けます。
この職種においては、以下のことが必要となります。
・データを分析する力
・統計学の知識
・プログラミングのスキル
UXデザイナー
まずUXとは「User Experience」の略語で、「ユーザーの体験」という意味になります。
ユーザーはアプリなどを経て様々な体験をしますが、UXデザイナーとは、そのアプリなどの立ち上げの際に「ユーザーの思考・ニーズに基づいてアプリなどのコンセプトを決定し、それを満たす体験を描くためのデザインを作成する人」です。
そのため、この職種では、以下のことが必要となります。
・デザイン力
・ユーザーの行動を読む力
・自分の中のイメージをアウトプットできる力
エンジニア/プログラマ
まずエンジニアには、ITエンジニア、インフラエンジニア、システムエンジニアなど様々な種類があり、「ほかの職種が設計したシステムなどを実装する人」です。
そのため、この職種では、以下のことが必要となります。
・基本的なプログラミングスキル
・DXにおける各言語のスキル
4.DX推進におすすめの資格

それでは実際に、おすすめの資格と、それを生かせる職種を見ていきましょう。
基本/応用情報技術者試験
「高度なIT人材となるために必要な知識・技能をもち、高度IT人材としての方向性を確立または実践的な活用能力を身に付ける」ための試験となり、基礎編と応用編の2種類があります。
試験時間・出題形式・出題数・解答数は次の通りとなります。
午前と午後に分かれての二部制となっており、
<午前>
・試験時間:150分
・出題形式:選択式(四肢択一)
・出題数 :80問
・回答数 :80問
<午後>
・試験時間:150分
・出題形式:選択式(応用情報技術者試験は記述式)
・出題数 :11問
・回答数 :5問
【この資格がおすすめの職種】
全職種
基礎の資格であるため、すべての職種におすすめです。
参考
基本情報技術者試験:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構:制度の概要:基本情報技術者試験
応用情報技術者試験:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構:制度の概要:応用情報技術者試験
AWS認定試験
この試験は、世界有数のAmazonが提供するものです。主にAmazonが提供しているWebサービス(AWS)についてのスキルを身に着けられ、様々な種類があります。
<基礎コース>
・クラウドプラクティショナー
<アソシエイト>
・ソリューションズアーキテクト
・シスオプスアドミニストレーター
・デベロッパー
<プロフェッショナル>
・ソリューションズアーティテクト
・デボプスエンジニア
<専門知識>
・アドバンスドネットワーキング
・データアナリティクス
・データベース
・マシーンラーニング
・セキュリティ
また、AWSだけでなく仮想サーバやPaasなどを活用する場合にはぜひ取っておきたい資格です。
【この資格がおすすめの職種】
・アーキテクト
・データサイエンティスト/AIエンジニア
・エンジニア/プログラマ
ITコーディネータ試験
ITコーディネータ試験は、ケース研修の受講と合わせて実施しています。
試験時間・出題形式・出題数・解答数は次の通りとなります。
・試験時間:120分
・試験方式:コンピュータを使用
・出題形式:選択式
・出題数 :必須 60問/選択 40問
サンプル問題や試験の対策講座もあるので、ぜひ下記の参考サイトをご覧ください。
【この資格がおすすめの職種】
・アーキテクト
・プロデューサー
・ビジネスデザイナー
ITストラテジスト試験
この資格は国家資格で、IT人材として経営戦略などを学べるものです。
試験は四部制となっています。
<午前Ⅰ>
・試験時間:50分
・出題形式:選択式(四肢択一)
・出題数 :30問
・回答数 :30問
<午前Ⅱ>
・試験時間:40分
・出題形式:選択式(四肢択一)
・出題数 :25問
・回答数 :25問
<午後Ⅰ>
・試験時間:50分
・出題形式:記述式
・出題数 :4問
・回答数 :2問
<午後Ⅱ>
・試験時間:120分
・出題形式:論述式
・出題数 :3問
・回答数 :1問
【この資格がおすすめの職種】
・プロデューサー
・ビジネスデザイナー
・アーキテクト
参考:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構:制度の概要:ITストラテジスト試験
AI実装検定
この試験は、AIを実装するための能力があるかを試すことができます。試験は3種類あります。
<S級>
応用的な実装能力を測る試験です。
・NLP :20問
・Model:30問
<A級>
基礎的な構造の理解力を測る試験です。
・AI :20問
・プログラミング :20問
・数学(高校レベル):20問
<B級>
AIの実装に関して、直感的な理解度を測る試験です。
・AI超入門:30問
【この資格がおすすめの職種】
・アーキテクト
・データサイエンティスト/AIエンジニア
・エンジニア/プログラマ
プロジェクトマネージャー試験
IT人材として、プロジェクトの達成に向けて、計画を作成し、それに基づいてプロジェクトを実行・管理する能力を測ることができます。
この試験もITストラテジスト試験同様に四部制になっています。
<午前Ⅰ>
・試験時間:50分
・出題形式:選択式(四肢択一)
・出題数 :30問
・回答数 :30問
<午前Ⅱ>
・試験時間:40分
・出題形式:選択式(四肢択一)
・出題数 :25問
・回答数 :25問
<午後Ⅰ>
・試験時間:90分
・出題形式:記述式
・出題数 :3問
・回答数 :2問
<午後Ⅱ>
・試験時間:120分
・出題形式:論述式
・出題数 :2問
・回答数 :1問
【この資格がおすすめの職種】
・アーキテクト
・プロデューサー
・ビジネスデザイナー
参考:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構:制度の概要:プロジェクトマネージャ試験
5.DX化を推進し、業務効率化をしよう
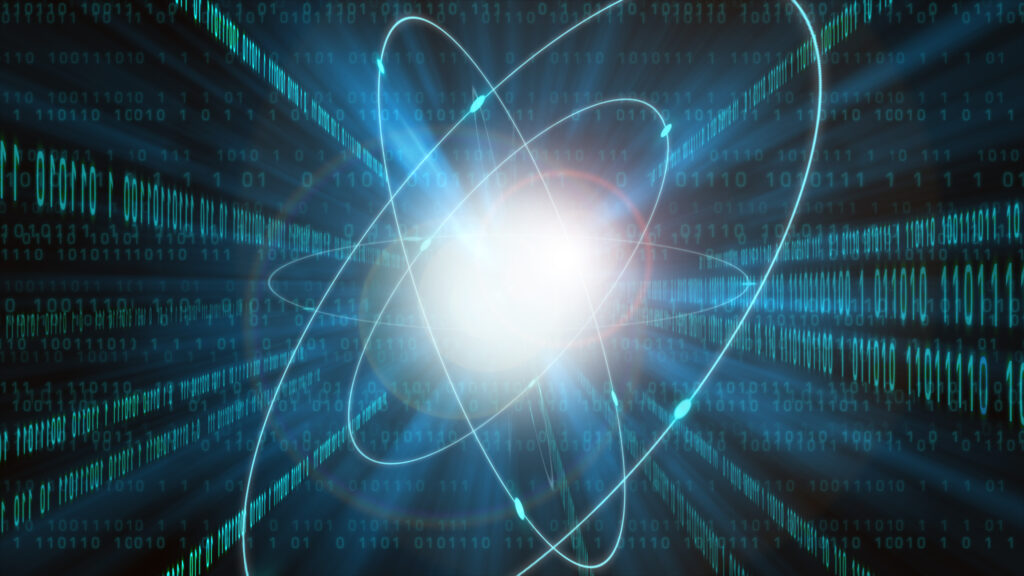
今回の記事では、様々な資格とそれを生かせる職種について紹介しました。職種についても簡単に述べましたので、社内のどういった人にどのような資格が必要か考え、実際に資格取得に向けて進めていく上で役に立つ内容にまとめました。
闇雲に資格取得を進めても費用がかかり、「コスト削減のために実施したのに無駄にお金を使ってしまった」という事態になりかねません。
的確に、無理なく無駄なく業務効率化を進めていくためにも、その人に合った資格をきちんと考えて、取得を推進していきましょう!


 DX Office
DX Office 



