
DX Office
DX支援を検討するなら、知っておくべきメリット・デメリット
最近耳にするようになったDXという言葉。聞いたことはあるけど、馴染みがなくてなかなか理解が出来ない、必要性が今一つ分からない、という方もいるのではないでしょうか。
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、テクノロジーにより産業構造を変化させること=ビジネスモデルを変化させることを意味します。
今一つピンとこない…。という方に、DXについてを分かりやすく説明していきます。
何故今DXが必要とされるのか、導入することでのメリット・デメリットやどのような支援があるのか。本記事を読むことでDXの構造から支援までを深く理解できるようになりますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
1.DX(デジタルトランスフォーメーション)について

DXとは
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、テクノロジーにより産業構造を変化させることを言います。
デジタル技術を導入することにより、業務を一元管理し目に見える形にすることで、社員が業務内容を把握できるようになり、より分かりやすく簡潔に行うことが出来るようになります。
また、デジタル化することにより情報の発信や予約システムを始め、様々なサービスを円滑に提供することが可能になります。
企業がDX導入を求められる理由
今日企業では様々な要因により、より進化したデジタル化やグローバル化への対応を迫られているため、DX導入が必要となってきています。
・スマホに続いてのAI普及による急激な変化やデジタル化
「センサーなどにより収集した情報をビッグデータ化し、AIを活用して分析することで小売り分野での需要予測、潜在需要を喚起する新商品・サービス開発、医療分野での予防医療やオーダーメイド医療、都市での犯罪・事故・災害抑制などの新たな価値の創造につなげることが可能になる」
・インターネット技術の発展によるビジネスモデルの変容
既存している6つの主要ビジネスモデル(物販、小売、広告、従量課金型、サブスクリプション、フリーミアム)から、SNSを利用した集客や広告、インターネットを利用した物販や映画館、美容院、病院、タクシー、飲食店、フードデリバリーなどの予約、VR版のアトラクション、映画や音楽、漫画や小説、洋服やバッグやアクセサリー、ラーメンやお酒、絵本やおもちゃなどの月額/年額といったサブスクリプションへの変貌を遂げています。
・雇用形態に捉われない働き方の多様化
フリーランス、フレックス、リモートワークなどの柔軟な働き方の実現、業務効率・生産性の向上、働きやすい環境の整備をはじめ、働く人々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現するのを目的とした働き方改革の推進が成されています。
・モバイル端末の発展に伴う情報の分散化
代表的なモバイル端末として、ノートパソコン、スマートフォン、タブレット、携帯型ゲーム機(PSP、Switch、DS、スマートウォッチ)などが挙げられ、ファミレスやコーヒーショップ、モバイルフォンショップなど街中でのフリーWifiスポットも多くなってきており、自宅でPCを通じて得られていた情報を時間や場所に捉われずに得ることが出来るようになっています。
2.DXを導入する上での課題とは
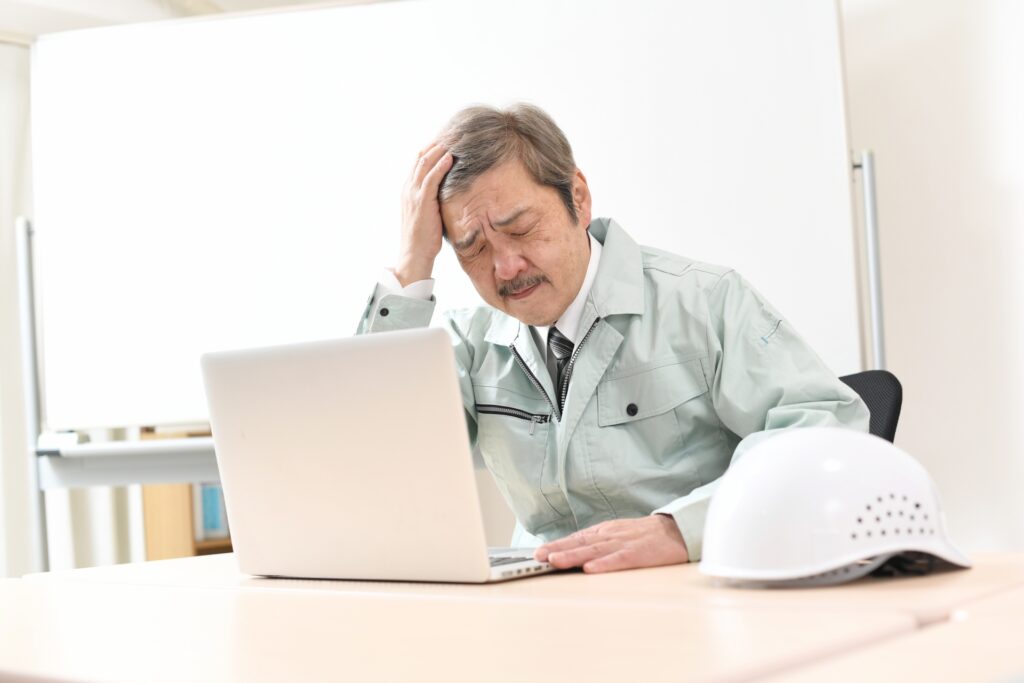
日本はITリテラシーが低い
日本人のITリテラシーは低いと言われています。リテラシーとは、literacy=読み書きの能力を意味しており、ITリテラシーとは、情報を正しく使うための能力、コンピュータを操作する技術、あるいは知識、ネットワークやセキュリティに関する技術的な知識を理解する能力の3つに分類されています。
日本では2007年頃より若年層を始めとしてスマートフォンが普及してきましたが、急激な普及率とは相反してITリテラシーの重要性が軽んじられてきました。
それだけではなく、欧米ではすでにスマ-トフォンなどのモバイル端末だけで仕事ができるようになっているのに対して、我が国ではモバイル端末の採用はまだ十分とは言えません。社内でも紙でやり取りすることも多く、いまだにFAXやメールがコミュニケーションの中心な企業も珍しくない状態です。最近になってやっとチャットが定着してきましたが欧米に比べ、IT技術の発展の遅さが否めません。
日本人ならではの商習慣
日本の商習慣もDXの浸透の大きな壁になっているとも言えます。紙媒体での回覧やハンコ文化はデジタルトランスフォーメーションを阻む大きな要因となっています。上司の了承を得て業務が進む指示形態は発案から実施までに時間を要し、報連相を大切にする日本人の勤勉さもスピーディーに解決するデジタル化とは相性が悪いと言え、DX推進に大きな隔たりを生み出しています。
日本には中小企業が多く(421万企業のうち99.7%)、2020 年時点での経営者の平均年齢は60.1歳となっており、労働人口6,667万人の約半数にあたる3,692万人は45歳以上であり、65歳以上の労働者も912万人と前年よりも15万人増加していることから窺えるように、労働人口の年齢が上がってきていることもデジタル化への足かせになっていると考えられます。
引用元:労働力調査(基本集計)2021年(令和3年)平均結果の要約
雇用制度や人事
日本企業は社員、契約社員、パート、アルバイト、期間職員、再雇用職員と言った様々な雇用形態で従業員を採用しており、業務内容が明確に規定されていないことや、業務を細分化し他社に委託するなども行われており、業務内容を各々に依存する形となっていることもデジタル化との軋轢を生じさせています。
人事でも評価制度に合わせて評価システムを導入することが主流であり、評価制度や人事制度を変えることは労働組合が存在する日本企業では大掛かりな改革になることが、DX化への困難さに繋がっていると言えます。
経営戦略が不明瞭
DX導入を検討してはいるものの目的や利点がはっきりしておらず、DXを導入することで社内・社外における業務で改善出来ることや簡略出来ること、サービスや利便性の向上など、何を行いたいかの具体的に検討出来ていないことが導入への妨げになっていると考えられます。
デジタル化に伴う人員不足
IT需要の高まりに伴い、今後社会全体で深刻なIT人材不足に陥ることが予想されています。このような状況下で社内システムをベンダー(IT製品をユーザーに販売する会社)に委託している企業が多く、既存システムの開発・運用についての知識を持つ人材が社内に存在しないことが大きな問題となっています。
予算投入に消極的
DX導入後のビジョンが不明瞭であることから、DX導入への予算投入にも消極的であるという問題点も挙げられます。
また、社内運用に必要とされる人員確保、育成に対しての予算投入されず、システム、人員での問題を抱えていると言えます。
成功率が低い
マッキンゼーが約1,200社を対象に行った調査によれば、日本企業のDXは全体の16%程度しか成功しておらず、製造、エネルギーなどのトラディショナルな業界での成功率は4~11%に留まっています。
DX推進には単にデジタル化をするだけではなく、企業の経営戦略、人員の確保、予算、働き方改革など、多岐に渡り見直す必要性があると考えられています。
引用元:マッキンゼーからの提言
3.DX導入のメリット

メリット① 業務効率の改善
作業内容を一元管理することにより、進捗状況などをネットワークを通じて社外からでも確認することが出来るようになります。さらに実施・未実施を確認することも容易になるため、人為的ミスを軽減できる効果が期待できます。
また、社員が個々で管理している顧客リストや名刺などの必要な情報を一元管理することにより、社内での情報の共有、社内連絡の迅速化が図れるようになります。
メリット②働きやすさの向上
紙媒体を使用する場合、相手の出勤状態に合わせての確認作業になったり、オフィスに出社する必要があったりしましたが、DXを導入することによりネットワーク管理が可能になるため、リモートワークでの業務遂行も可能になります。
リモートワークが可能になることで通勤時間を割けるようになり、社員の通勤による時間の拘束の軽減が図れる他、勤務形態の選択が広がることにより、産休や育休などを利用する社員や傷病により通勤が困難な社員に対し、柔軟な対応が可能になります。
メリット③経費削減
ネットワーク管理を行うことにより、ペーパーレスとなります。プリンターの使用頻度も低くなることから、紙やプリンターのインク代の削減、オフィス内でのファイル類の保管場所の削減などの効果が期待できます。また、紙媒体を管理するのに必要であった人件費や管理コストの削減も望めます。
4.DX導入デメリット

デメリット① 2025年の壁
IT人材の不足やレガシーシステムの保守切れにより、動かないシステムが発生することで国として年間最大12兆円程度の損失が生まれることを意味しています。
レガシーシステムとは、メインフレームやオフコンと呼ばれるコンピュータを使ったシステム・属人化が進んだ結果、社内に詳細を把握する人材のいないシステムなど、変化に対応するための柔軟性のないシステムのことを言います。
その多くは縦割りの事業部門ごとの業務に合わせて独自の仕様で構築されており、時間の経過に伴ってさらに独自のカスタマイズが重ねられ、肥大化・複雑化・ブラックボックス化が進んでいます。
DXレポートでは、国内の企業の約8割が今もこうしたレガシーシステムを抱えており、その保守・運用のために貴重なIT人材資源が浪費されていると指摘しています。
DXレポートでは、2025年以降、国内で年間最大12兆円の経済損失が生じる可能性があるとして強い警告を発しており、それを「2025年の崖」と称しています。
2025年になると、「レガシーシステム(企業が保有する最も大きなシステム)が21年以上前から稼働している企業」の割合が6割以上を占めるようになると予測され、年間12兆円の経済損失というのは、主にこのレガシーシステムを抱え続けることに起因する損失だと言われています。
引用元:「DXレポート~ITシステム『2025年の崖』の克服とDX の本格的な展開~
デメリット②システム管理の高額化
システムを維持することによる費用が高額になると言われています。一般的な保守だけではなく、故障・事故時の対処、セキュリティ対策の整備などにもコストはかかりますし、システム管理をするのに必要な人件費も同様にかかってきます。
企業のIT予算のほとんどがこうしたシステムの維持管理や人件費のために費やされているとも言われています。
既存システムが正常に機能し、企業の利益に貢献しているのであれば問題はないかも知れませんが、現状では大半のケースで既存システムは業務効率を低下させる要因になていることから、今後ますますその傾向が強まることが懸念されています。
デメリット③ 業務効率が悪い
「紙+郵送/Fax」といった紙媒体や印鑑・郵便送付/FAX送信など手作業が多くなると、確認作業も含め作業が煩雑化することがあります。更に少人数での作業では個人にかかる負担が多くなり、複数人での作業では業務の遂行状況の把握がしにくいことが挙げられる他、送付(送信)先間違いや内容物混入といった人為的ミスが起こることが考えられます。
5.DX支援サービスについて
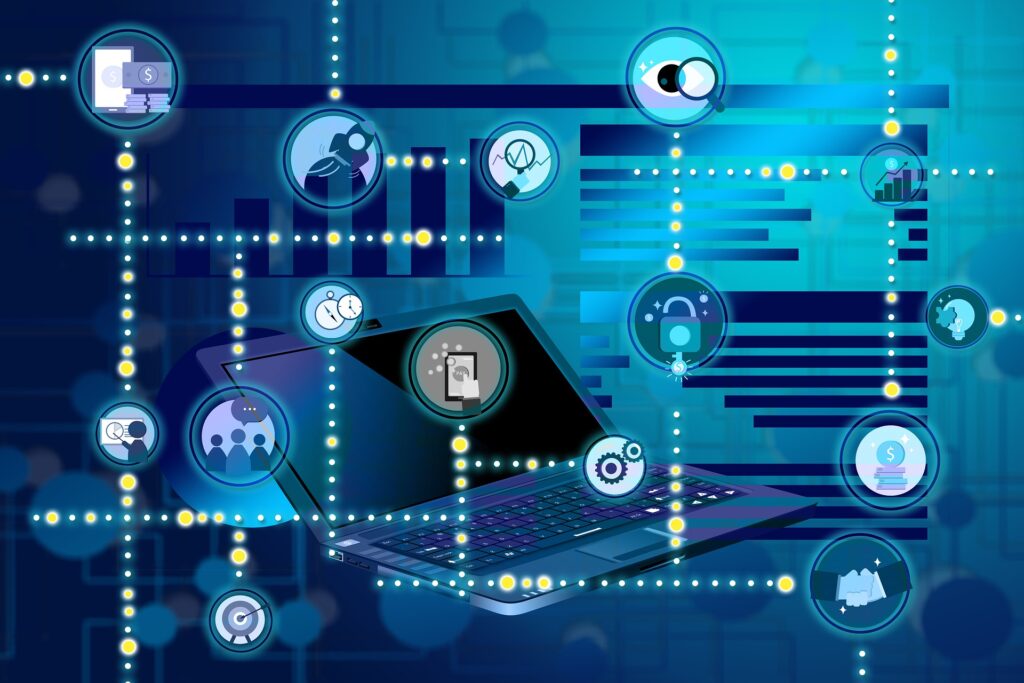
支援サービスの種類
・ビジネス変革支援(52.6%)
・IoT*1活用支援やSNS/ソーシャル技術活用支援、サイバーセキュリティ支援などを含むその他のデジタル技術活用の支援(38.2%)
・デジタルマーケティング/デザインの支援(28.9%)
・データ分析/AI活用/児童の支援(28.4%)/
約8割が何らかの支援サービスを利用しており、最多は「ビジネス変革支援」の52.6%となっていることから、技術支援よりビジネス変革支援が人気であることが伺えます。
「ビジネス変革支援」では、特に「DX人材の育成/リスキルの支援」「業務プロセスの変革/Business Process Re-engineeringの支援」「デジタル戦略の策定/デジタル事業開発の支援」が人気になっています。
引用元:ZDnetjapan「DX支援サービスは技術系よりビジネス系が人気–IDC調査」
*1 「IoT」とは、複数の機械などがネットワーク環境に接続され、底から収集される各種情報・データを活用して、1.監視(モニタリング)、2.保守(メンテナンス)、3.制御(コントロール)、4.データ分析(アナライズ)などを行うことを指します。単に従来から行われている単独機械の自動化や工程内の生産管理ソフトのみの導入は除きます。
国からの支援
日本では、各企業がDXを推進しやすいように様々な支援を実施しています。
①DX推進指標
DX推進指標とは、DXが自社においてどのくらい進んでいるか自己判断するための基準を示したものです。
【使い方】
1.認識共有・啓発 ⇒ 2.アクションにつなげる ⇒ 3.進捗管理
1.認識共有・啓発
「DX のための経営の仕組み 」と「その基盤としての IT システムの構築 」に関 して、経営幹部や事業部門、DX 部門、IT 部門などの 関係者が集まって議論しながら、関係者の間での認識の共有を図り 、今後の方向性の議論を活性化すること
(注:担当者が 一人で回答するだけでは 、関係者間の 認識の共有につながらない 、また、IT 部門の評価結果を事業部門が確認し、さらにその結果を経営幹部が 6 レビューする、という一方通行の回答方法の場合にも、関係者間の十分な認識 の共有につながらない)
2.アクションにつなげる
自社の現状や課題の認識を共有した上で、あるべき姿を目指すために次に何をするべきか、アクションについて議論し、実際のアクションにつなげること
(注:各項目に点数を付けるだけではなく 、アクションについて議論し、実際 のアクションにつなげることが重要)
3.進捗管理
翌年度に再度診断 を行って、アクションの達成度合いを継続的に評価 すること により、DX を推進する取組の経年変化を把握し、自社の DX の取組の 進捗を管理 すること
(注:一度診断を行っただけでは 、持続的な DX の実行につながらない 、また、 年次ではなく、より短期のサイクルで確認すべき指標、アクションは自社のマ ネジメントサイクルに組み込んで管理することが重要)
・DX 推進指標の概要
<構成>
本指標は、DX の推進に際し、現在の日本企業が直面している課題やそれを解決するた めに押さえるべき事項を中心に、以下のとおり構成される。
1) DX 推進のための経営のあり方、仕組みに関する指標 (「DX 推進の枠組み」(定性指標)、「DX 推進の取組状況」(定量指標))
2)DX を実現する上で基盤となる IT システムの構築に関する指標 (「IT システム構築の枠組み」(定性指標)、「IT システム構築の取組状況」(定量指標))
定性指標は、指標ごとにクエスチョンが設定されており、以下の 2 種類で構成される。
キークエスチョン: 経営者が自ら回答 することが望ましいもの。
サブクエスチョン: 経営者が経営幹部、事業部門、DX 部門、IT 部門などと議論をしながら回答するもの。
<定性指標における成熟度の考え方 >
本指標のうち定性指標においては、DX 推進の 成熟度を 6 段階で評価 する。本指標が日本企業の国際競争力を高め、デジタル企業への変革を促すことを目的としていることから、最終的なゴール(レベル5)は「デジタル企業として、グローバル競争を勝ち抜くことのできるレベル」とする。
本成熟度を利用することで、自社が現在どのレベルにいて、次にどのレベルを目指すのかを認識するとともに、次のレベルに向けて具体的なアクションにつなげることが期待される。
引用元:経済産業省『「DX 推進指標」とそのガイダンス:図1「DX 推進指標」と各社指標との関係』)
②補助金・助成金制度
企業のDX実現に必要なデジタル関連投資に対する優遇税制として、2021年度の税制改正において新設された制度です。
引用元:DX投資促進税制の導入── 2021年度(令和3年度)税制改正における企業のデジタル化を支援する税制①
③IT導入補助金
中小企業・小規模事業者など(飲食、宿泊、卸、小売、運輸、医療、介護、保育などのサービス業のほか、製造業や建設業なども対象)
<補助対象者>
中小企業・小規模事業者など(飲食、宿泊、卸、小売、運輸、医療、介護、保育などのサービス業のほか、製造業や建設業なども対象)
<補助対象経費>
ソフトウェア費、導入関連費(引用元サイトにて公開予定のITツールが補助金の対象です)
引用元:IT導入補助金 2021年
④ものづくり・商業・サービス生産性向上補助金
ものづくり・商業・サービス生産性向上補助金は、中小企業の・小規模事業者などが今後複数年に渡り相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用の拡大、賃上げ、インボイス導入など)などに対応するため、中小企業・小規模事業者などが取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資などを支援するものです。
引用元:ものづくり補助事業公式ホームページ ものづくり補助金総合サイト
⑤事業再構築補助金
事業再構築補助金新分野展開、業態転換、業種転換、事業再編またはこれらの取り組みを通じた規模の拡大など、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業などの挑戦を支援したものです。
引用元:事業再構築補助金
その他の支援
企業規模での検討をしてコンサルタントに相談する。
DX支援企業に依頼する企業規模の目安は従業員100名と言われており、自社内の連携・DXが複雑であればあるほど費用対効果を得られやすくなると考えられています。企業規模の小さい場合はコンサル費用の割に合わない効果しか得られない可能性があるので、SaaSなどの各種システム導入で局所的に改善していく方が効率的だと言えます。
6.DX導入及び支援について

DXとは、世界的なグローバル化に伴い、急加速をするデジタル技術への対応を迫られている状況の中、ITリテラシーの見直し、作業効率に対する企業の方向性など、点在していた業務を一元化することでもあり、自らの手で触れて確認をしながら行って来た業務をデジタル化することでもあります。
IT普及が始まってから感じたことがない問題が生じてくることも考えられ、中には慣れ親しんできた業務の手順が変わることへの戸惑いを感じる方もいるでしょう。
しかし、デジタル技術は留まることなく更なる進化を続けています。
DXを導入することで得られるメリットに着目し、適切な支援を利用して、この先の企業の躍進を担うこととなるDX導入を考えてみてはいかがでしょうか?


 DX Office
DX Office 



